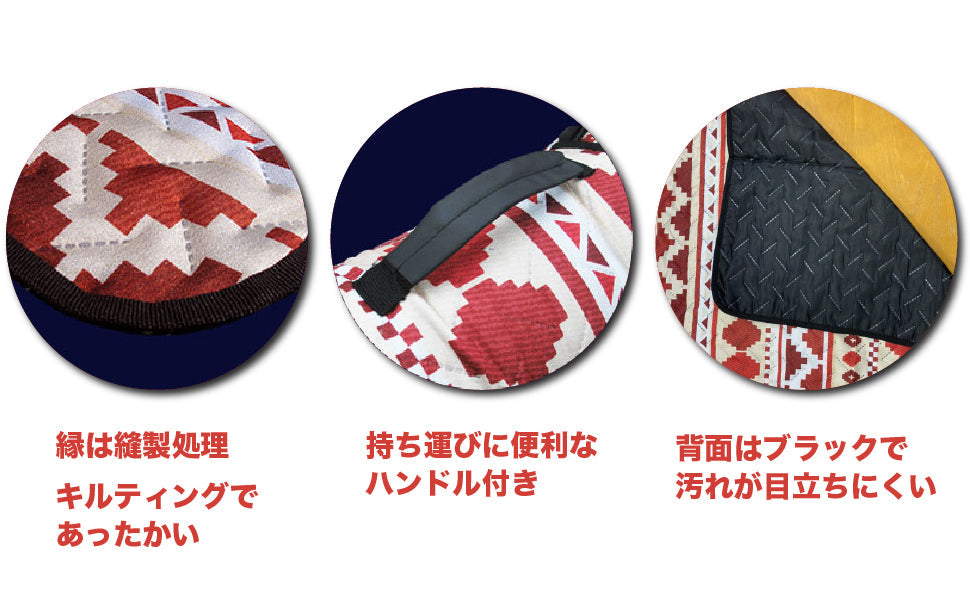はじめに
ベビーサークルは、赤ちゃんの安全と自由をうまく両立させてくれる便利なアイテムです。しかし、赤ちゃんの成長には個人差があり、ベビーサークルの適切な使用期間は赤ちゃんによって異なります。本記事では、ベビーサークルの使用時期やその判断基準、卒業後の対策など、ベビーサークルに関する情報を詳しく解説していきます。
ベビーサークルを使い始める時期
ベビーサークルの使用を開始する適切な時期は、赤ちゃんの発達段階によって変わってきます。一般的には、以下の時期からベビーサークルを導入することが多いようです。
ハイハイを始める頃
赤ちゃんがハイハイを始める頃、つまり生後6ヶ月前後からベビーサークルを使い始めるのが一般的です。この時期になると、赤ちゃんの行動範囲が広がり、家の中を自由に動き回るようになります。ベビーサークルを設置することで、安全な空間を確保しつつ、赤ちゃんの探索心を満たすことができます。
ベビーサークルの導入に際しては、徐々に赤ちゃんに慣れさせることが大切です。最初は嫌がる赤ちゃんもいますが、ママやパパと一緒に遊ぶうちに、ベビーサークルが楽しい遊び場だと感じられるようになります。
つかまり立ちを始める頃
つかまり立ちを始める頃、つまり生後8ヶ月前後からベビーサークルを使い始める家庭も多い傾向にあります。この時期になると、家具につかまって立ち上がるようになりますが、それだと家具ごと倒れるなどの危険も伴います。その点ベビーサークルはつかまり立ちの練習にも最適です。
また、サークル状にしてあればサークルをつたってぐるりとつかまり立ちしても安全です。ベビーサークルを設置することは、つかまり立ちの練習や危険回避に一役買うのです。
そして、ベビーサークルの高さは、つかまり立ちをする赤ちゃんが乗り越えられない程度の高さが適しています。メーカーの推奨サイズを参考にしながら、赤ちゃんの成長に合わせて選ぶことが重要です。
歩行を始める前から
歩行を始める前の時期、つまり生後10ヶ月前後からベビーサークルを導入するのも一つの選択肢となります。歩行が始まると赤ちゃんの行動範囲がさらに拡大するため、ベビーサークルを設置して、赤ちゃんにとって安全な環境を整えることが必要になります。
ただし、すでに自我が芽生え始めている時期でもあるため、ベビーサークルを嫌がる赤ちゃんも少なくありません。この場合は無理に使用を強要せず、赤ちゃんの様子を見ながら柔軟に対応しましょう。
また、歩行し始めてからやっぱりベビーサークルを導入しよう、という方も多いでしょう。赤ちゃんの成長を見ながら適切なタイミングで導入することが大切です。
ベビーサークルの使用期間
ベビーサークルの使用期間は、赤ちゃんの成長に合わせて柔軟に対応することが需要です。一般的には以下の期間が目安とされています。
1歳半頃まで
多くのご家庭では、ベビーサークルを1歳半頃まで使用しているようです。1歳半頃になると、赤ちゃんの運動能力が高まり、ベビーサークルの中で遊ぶよりも家の中を自由に動き回りたがるようになります。
また、この頃になると自我がしっかりと芽生え、ベビーサークルに入るのを拒否したり、サークルの中にずっといるのを嫌がったりすることも少なくありません。そんな時は赤ちゃんではなくテレビや棚など触って欲しくないエリアをサークルで囲うと良いでしょう。
成長に伴って使用方法・環境を変えてあげることが大切です。
2歳頃まで
ベビーサークルは、赤ちゃんの成長に合わせて柔軟に使用期間を延長することもできます。一般的には2歳頃までの使用が可能とされています。
2歳頃はお子様によって性格や成長が異なるので、嫌がらないようであれば使用を継続し、嫌がったり、サークルを力一杯揺らすなど危険がありそうな場合は卒業しましょう。
個人差による柔軟な対応
ただし、赤ちゃんの成長には個人差があるため、上記の目安はあくまでも参考程度にとどめましょう。実際には、赤ちゃんの行動や体の成長を見守りながら、適切な卒業時期を判断することが重要です。
1歳を過ぎた頃から既にベビーサークルを乗り越えようとする赤ちゃんもいれば、2歳を過ぎてもベビーサークルの中で安心して遊ぶ赤ちゃんもいます。赤ちゃん一人ひとりに合わせて、柔軟に対応することが大切です。
ベビーサークルの活用方法
ベビーサークルには、単に赤ちゃんを囲って安全なスペースを確保するだけでなく、さまざまな活用方法があります。赤ちゃんの成長に合わせて使い方を工夫することで、より便利に、長く活用できます。
パネルの追加・削減でスペースの調整
ベビーサークルには、パネルを増減させてスペースを調整できるタイプがあります。赤ちゃんが小さい頃は狭めに、成長に合わせて拡張パーツを追加して広げていくなど、柔軟に対応できます。
また、パネルを上手く組み合わせることで、部屋の一部を区切ることもできます。例えば、テレビ周りを囲んで危険を防いだり、キッチンスペースを確保したりと、用途に合わせて活用できます。

キッズパーテーションとしての活用
ベビーサークルを卒業した後も、パネルを生かしてキッズパーテーションとして使うことができます。子供部屋と居間を仕切ったり、プレイスペースを区切るなど、活用の幅が広がります。
キッズパーテーションとして使えば、子供の遊び場を確保しつつ、見守りやすくなります。成長に合わせて、子供の行動範囲を調整できるのも大きなメリットと言えるでしょう。
上の子の遊び場としての活用
兄弟がいるご家庭では、上の子の遊び場としてもベビーサークルは活躍します。なんでも口に入れてしまう時期の赤ちゃんがいると、上の子はレゴやプラレールなどの細かいおもちゃで遊ぶのが難しくなり、好きな遊びを我慢することも少なくありません。
そこで、ベービーサークルを上の子専用の遊び場として使うことで、サークル内に好きなおもちゃを広げて、遊びたいおもちゃで思いっきり楽しめます。そうすると赤ちゃんが誤飲する心配もなく、赤ちゃんと上の子がどちらも快適に過ごせて安全に遊べる環境を作ることができます。
ベビーサークル卒業後の対策
ベビーサークルを卒業した後も、子供の安全を守るための対策が必要になります。家の中には様々な危険が潜んでいるため、適切な環境を整えることが重要です。
家具の角や引き出しへの対策
活発に動く時期になると特に心配になるのが、家具やテーブルの角。ふらついた拍子にぶつけてしまったり、不意に当たってしまいケガをしないか不安に感じるママやパパも多いのではないでしょうか。家具の角には、コーナーガードを取り付けて対策をしましょう。
子供の手が届く位置にある引き出しや戸棚に安全ロックを設置することも、思わぬ事故防止につながります。
また、この時期に家具を見直すのも一つの手です。角が鋭利でないタイプの家具に変更したり、思い切ってリビングには家具をあまり置かないという選択肢もあります。安全のために環境を整えましょう。
おもちゃの安全性の確認
子供が遊ぶおもちゃの安全性も確認しましょう。小さな部品があるものは、誤飲の危険があるため注意が必要です。行動範囲が広がる分、おもちゃの整理整頓も心がけましょう。
また、プラスチック製のおもちゃは、遊び方の影響や老朽化によって割れる危険性があります。ヒビ割れや欠けた部分がないか定期的に点検し、古くなったら交換するようにしましょう。
子供の行動範囲の制限
ベビーサークルを卒業しても、行動範囲を適切に制限することが重要です。しっかり見ているつもりでも、ふと目を離した隙に怪我をしてしまうこともあるため、危険な場所には立ち入らせない工夫が必要です。
また、子供が危険を理解できるようになるまでは、危険な物を手の届かない場所に保管するなどの対策も必要です。
特に小さな頃は、昨日までできなかったことがある日突然できるようになることの繰り返しです。なので、産まれてからの数年間は子供の成長に合わせて住環境や生活スタイルを柔軟に変化させることが必要です。
サークルを卒業した後も子供の成長に沿って安全対策をしましょう。
まとめ
ベビーサークルは、赤ちゃんの安全と自由を両立させてくれる便利なアイテムですが、適切な使用期間を守ることが大切です。一般的には生後6ヶ月から1歳半頃までの使用が多いようですが、赤ちゃんの成長には個人差があるため、柔軟に対応しましょう。
ベビーサークルを卒業した後も、家具の角や引き出しへの対策、おもちゃの安全性の確認、危険な場所への立ち入りの制限など、様々な安全対策が必要になります。赤ちゃんの健やかな成長のために、ベビーサークルの使用期間と活用方法、安全対策を適切に行うことが大切です。
PARKLON JAPANは韓国発の人気ベビー用品メーカーの公式ショップです。機能的でデザイン性にも優れた製品を多数取り揃えており、世界中のママやパパたちに支持されています。ぜひ商品をチェックしてみてください。